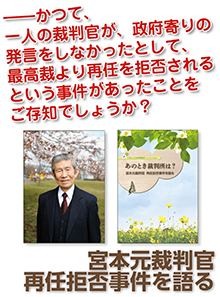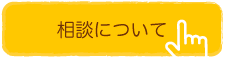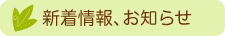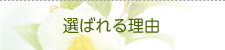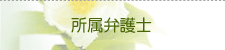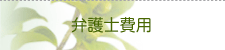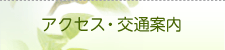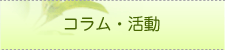コラム47:戸籍のイロハ
2016.5.17 弁護士 松縄 昌幸
先日、法律事務所の事務局員向け研修ということで、戸籍に関する基本的事項(戸籍のイロハ)について講義をさせていただきました。戸籍については、普段は触れる機会がなく知識がない方でも、相続の手続のために集めなければならなくなるということが往々にしてありますが、なかなか大変な作業です。
【相続事件で「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」が必要な理由】
相続に関し、金融機関で相続の手続を行う際や相続人間での話し合い(遺産分割協議)がまとまらず裁判所に遺産分割調停の申立てを行う等の際、少なくとも、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」の提出を求められます(プラスして求められる戸籍の範囲は、相続人の立場によって異なります)。これは、相続人が誰であるかが確定できないと、誰を手続に関与させる必要があるのかわからず、手続が進められないからです。相続人の確定は大前提なのです。
配偶者は常に相続人となり(民法890条)、子がいる場合には、配偶者とともに子が相続人となりますが(民法第887条1項)、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」が必要とされるのは、第一順位の相続人である子の有無等を確定するためです。現在の戸籍に出生から死亡までの身分事項が全て記載されているのであれば、その戸籍を見ただけで子の有無等が確認できます。しかし、多くの場合、亡くなった方(被相続人)はある程度の年齢に達しており、古い戸籍から新しい戸籍に移動しています(現在の戸籍法では、結婚すると新しい戸籍を作ることになりますし、平成6年の戸籍のコンピュータ化に伴い、新しく戸籍が作成されています)。そして、現在の戸籍制度では、新しく戸籍が作られる際、身分事項に関する履歴が全て新しい戸籍に記載されるわけではなく、新しい戸籍に移記されない事項があります。
例えば認知ですが、現在の扱いでは、婚外子は出生すると母親の戸籍に入り、父親が認知をしてもその子は父親の戸籍に入るわけではありません(母親の戸籍に入ったままです)。そして、父親の戸籍には、「身分事項」という欄に認知に関する事項が記載されるに過ぎません。しかし、その後、父親につき何らかの事情で新しい戸籍が作られ父親がその戸籍に移った場合、この認知に関する事項は新しい戸籍に移記されません。そのため、もちろん認知した子も相続人なのですが、新しい戸籍を見ただけでは、その存在がわかりません。
【戸籍を遡るという作業】
このように、現在の戸籍を見ただけでは、子の有無等の確定ができません。そこで、過去の戸籍を遡って見ていく作業が必要となります。
遡って見ていく際には、その戸籍がいつからいつまでの戸籍なのか(いつ作られていつ消除されたものなのか)、集めた戸籍間に空白期間がないかどうかを確認することが必要になります。空白期間があると、その間に子ができていることがあるためです。そのため、「被相続人の出生から死亡までの『連続した』戸籍」を確認することが必要になるのです。
実際に遡って見ていく場合、具体的には、まず現在の戸籍を出発点としてその一つ前の古い戸籍を取り寄せ、そこからさらにもう一つ前の古い戸籍を取り寄せていくというかたちで、順次古い戸籍を集めていくことになります。その際、空白期間を生じないためには、その戸籍がいつ作られていつ消除されたものなのかを正確に判断する必要がありますが、そのためには、どのような出来事があると戸籍が作られ(戸籍の編製原因)、どのような出来事があると戸籍が全部削除されることになるのか(戸籍の消除原因)を理解しておく必要があります。もっとも、この戸籍の編製、消除原因は昔からずっと同じわけではなく、古い戸籍と新しい戸籍とで異なります。これは、戸籍制度の変遷に関係しています。
【戸籍制度の変遷】
戸籍制度は、時代の流れとともに変わってきました。最初に作られた戸籍制度は、明治5年式戸籍(壬申戸籍)と言われています。その後、戸籍の様式が法律や命令によって改められた際、古い様式のものを新しい様式に作り替える作業(「改製」と言います。)が何度か行われました。改製後の戸籍は、それぞれ明治19年式戸籍、明治31年式戸籍、大正4年式戸籍と呼ばれています。これら戸籍(旧戸籍)においては、「家」、つまり「戸」(戸主とその家族で構成された世帯)を単位に戸籍が作られていました。というのも、この頃には家制度が存在していて、戸主には家族の婚姻、縁組みへの同意権等が認められており、戸主は特別な地位にありました。そのため、戸主を基本として戸籍が作られていました。
ところが、日本国憲法、現行民法が施行され、家制度は廃止されました。昭和23年1月1日から現行戸籍法が施行されましたが、これにより、戸籍の単位は「一つの夫婦及びこれと氏を同じくする子」に変わりました(現行戸籍)。
また、その後、役所の職員がタイプや手書きで紙に書き保存していたものが、平成6年のコンピュータ化により、磁気ディスクで管理されるようになりました。
【戸籍の編製、消除原因】
戸籍制度の変遷は上述のとおりですが、古い戸籍(旧戸籍)では、戸籍制度が家制度と結びついていたため、戸主を基本として戸籍が作られており、戸主が交代すれば前戸主の戸籍は消除され、新戸主の戸籍が編製されました。そこで、家督相続(戸主の交代)が主な戸籍の編製、消除原因となっていました。また、新しい家が設立されれば新しい家につき新戸籍が編製され、家が消滅すれば戸籍は消除されました。
これに対し、昭和23年1月1日戸籍法施工以降の新しい戸籍では、戸籍の単位が「一つの夫婦及びこれと氏を同じくする子」に変わったため、日本国籍を有する者の間で婚姻の届出があったとき等に新しく戸籍が作られることになりました(一つの夫婦という、戸籍の単位が新しくできるためです)。
このように、古い戸籍と新しい戸籍とで、戸籍の編製、消除原因が大きく変わりました。
なお、古い戸籍でも新しい戸籍でも、市町村をまたいで本籍地を移動した場合(「管外転籍」と言います。本籍地の移動は自由にできます)、転籍先で新たに戸籍が作られ、転籍元の戸籍は削除されます。これは、戸籍の管理は市町村毎とされているためです。また、戸籍の様式変更(前述の改製)があった場合も、従前の様式の戸籍は消除され、新しい様式の戸籍が作られます。
【最後に】
このように、戸籍には新しく作られる原因と消除される原因がそれぞれ決まっています。戸籍を見る際、これら原因がどのように記載されているかを見て、その戸籍がいつからいつまでの戸籍なのかを判断した上、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」を集めて初めて、相続手続を進めるにあたっての大前提を満たすことができます。特にコンピュータ化前の戸籍は文字が読みづらいこともあり、スタートラインに立つことさえ大変な面があります。そのため、戸籍の収集は専門家に任せてしまう、というのも手です。