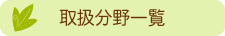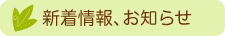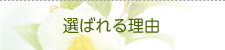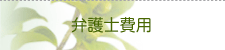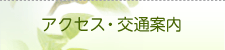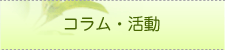コラム44:ミステリーの中の司法制度
2015.8.5 弁護士 岸 敦子
シャーロック・ホームズやアガサ・クリスティー作品(名探偵ポワロやミス・マープル)が好きで、映像化されたものもよく見ます。読み始めた(見始めた)小学生のころは気にしていませんでしたが、最近は時々、日本とイギリス(イングランドとウェールズ?)の制度や文化の違いを感じることがあります。
これらの作品には、「検死法廷」(「検死審問」や「査問」と訳されたりもしています)というものが時々出てきます。作品中では人が死にますが、そこで公開の検死法廷が開かれて、遺体を見た医師が死因について所見を述べたり、被害者の友人が生前の様子(自殺の兆候があったかどうかなど)について話したりしています。それを受けて、被害者の死因について法廷が何らかの結論(自殺、殺人など)を出します。検死官が手続をして、陪審で行われるようです。
日本では、死因は警察が捜査をはじめるかどうかの重要な判断材料ではありますが、検死法廷は存在しません(検死法廷かどうかは別として、解剖医の不足は以前から指摘されているので、死因を明らかにするための制度は充実したほうが良いように思います。)。
また、殺人の動機に関連してよく「遺言」が出てきます。「被害者は殺される○日前に弁護士に連絡して遺言を書き換えていた。それによると遺産はAに渡る(だから、犯人はAかも)。」というのが典型例です。探偵が弁護士から遺言内容を聴取する場面もよくあります。作品の中の出来事で、このような場合の被害者はだいたいが資産家ですので割り引いて見るべきとは思いますが、イギリスの人々はごく普通に弁護士を利用して遺言を作り、また、その内容を変更しているような雰囲気がありました。何かの作品で若い女性の登場人物が既に遺言を作っていたので驚いたこともあります。
もちろん日本にも遺言はあるのですが(作ることをオススメします)、イギリスに比べると一般的ではないような気がします。昔からの習慣や文化の違いが大きいのでしょうが、イギリスは遺言を作りやすいような制度設計がされているのかもしれません。
この他にも、「巡回裁判」とか「治安判事」とか、いろいろと知らない言葉が出てきます(知らなくても小説は十分に楽しめます)。あくまで小説の中のことですし、19世紀末や20世紀前半の作品ですので現代とは違う部分もあるでしょう。その違いも含め、諸外国の制度や文化、日本との違いや共通点を考えながら作品を鑑賞するのも、楽しいのではないでしょうか。