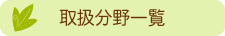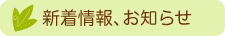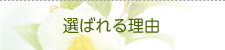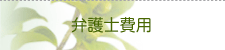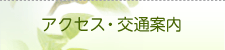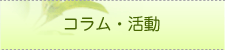免田事件が残したものは
もう1年半ほど前のことになりますが、免田栄さんが、95歳で亡くなりました。というだけでは、誰のことか分からないという方も多いかもしれません。死刑判決が確定していたにもかかわらず、1983年7月15日に一転裁判のやり直し(再審)で無罪になり「自由社会」に帰ってこられた方、といえばどうでしょう。そう言われてみれば、と思い出される方もいらっしゃるかもしれませんが、もうじき無罪判決から39年になりますから、何を今さらと思われるかもしれません。
確かに、多分に個人的な関心からのお話しで申し訳ありませんが、あらためて免田事件のことを振り返ってみようと思ったのは、今年になってから、無罪判決後免田さんと親しく交流を続けていた地元熊本の新聞記者が免田さんの評伝を公にしたからでもあります(高峰武『生き直す・免田栄という軌跡』弦書房)。評伝自体は、無罪判決後の37年、ひいては95年の人生が語りかけるものは何か。身近にいた者が知り得た様々なエピソードを交えて、元死刑囚の生き様を伝えています。死刑執行の恐怖との闘いだった獄中生活。無罪後も、強いられた「虚偽自白」の弁明を求める「刺すような視線」に苛まれた日々。その中で、初の死刑再審無罪者として死刑廃止と冤罪救済へ「本当の民主主義、人権意識を社会の中にどう根付かせるか」が、「一生をかけた仕事」との覚悟をもって生き抜いたことが分かります。
問題は、そのような個人の覚悟を超えて、免田事件がどのような歴史的な意味を持つことになったのかです。実は、1980年代には、免田事件に続いて他にも3件の死刑確定事件が再審で無罪になりました。刑事司法にとっては極めて深刻な事態でした。とりわけ免田事件は、再審での無罪判決の理由が、アリバイの存在でした。しかも、その根拠は、既に捜査段階から存在していた証拠でした。何故そんなことが起こったかと言えば、長期間拘束し自白を迫るという「人質司法」と言われる自白偏重の刑事手続にあるということが、あらためて指摘されることにもなりました。免田さんは、夜中に連行・逮捕され、三日三晩まともに睡眠を取ることも許されず、弁護人の援助を受けることもできず、虚偽自白に追い込まれるということになりました。その虚偽自白が、偏重され、アリバイ証拠を乗り越えていったのです。そのような事態は、高名な刑事法研究者をして「わが国の刑事裁判はかなり絶望的である」と言わしめることにもなりました。
そしてその後の裁判員制度の導入といったことにもなった刑事司法改革のきっかけにもなりました。
しかし、無罪判決から40年近くを経て、「人質司法」と批判されてきた身体拘束制度は、いっこうに改革されていません。弁護士のボランティアではじまった当番弁護士は、なんとか被疑者段階の国選弁護制度を実現することにはなりましたが、最も弁護人の援助が必要な逮捕段階には、まだ国選弁護は認められていません。そのため、逮捕段階には相変わらず、ボランティアの当番弁護士が対応していますが、充分に対応できているとは言えません。
それに、「生き直す」ことを不可能にする「死刑だけはなくしてほしい」との免田さんの遺言の実現には、世界の趨勢に反し、なお道遠しという状況です。あらためて刑事司法改革が不可欠だと言わざるを得ません。